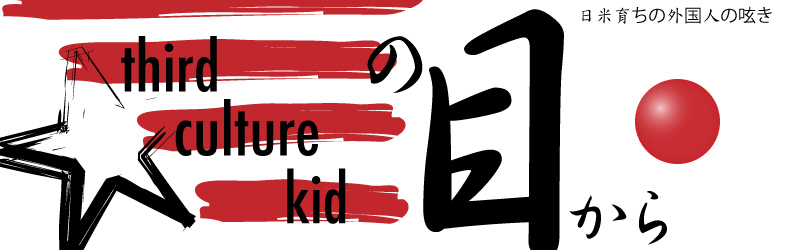| Picture Courtesy of Sean Dreilinger |
2010年10月3日
親の責任?学校の責任?
2010年9月13日
日本の教育はこれで良いのかな?
| Image courtesy of Dylan James |
僕は何も変わらないと思う。なぜかと言うと問題はゆとり教育ではないと思うからである。世界1の教育を誇るフィンランドの教育制度は日本のゆとり教育に近いからである。フィンランドも週5日制度で、授業時数は日本とほぼ同じ。そしてゆとり教育で始まった「総合的な学習」時間は日本より多い。日本はフィンランドの教育制度を真似しようとしていたけど、何かの理由で同じ成果をだせない。
皆さんはこれが何が原因だと思いますか?
2010年9月1日
いじめはどうして起こる?
| Image courtesy of Hekate-moon |
皆さんはいじめがどうして起こると思いますか?
僕は最近まで次のように考えていた。いじめっ子は自尊心が低くて、周りの子をいじめることでと自分の気持ちが楽になる。自分の弱さが嫌いだから、もっと弱い子をいじめ、自分に力あると思うるためにいじめをする。それか、自分がいじめられたから、自分を守るために他の子をいじめる。つまり、いじめっ子は自分の中の足りない部分を埋めるためにいじめをすると思っていた。でも、最近の調査でそうではないと分かった。
2010年8月29日
2010年8月22日
自分や自分の親の理解を深める子育て
| Image courtesy of Into Somerset |
皆さんの親はどんな親だったのだろうか?僕は日本で様々な人と話して、いろんな親の例を見た。この経験から、今子育てしている人の親がステレオタイプとして、この次のような親だったのではないのかと思う。
2010年8月17日
自分の理解から
親は子供を理解する為には何をしたら良いと思う?僕は親自らが自分自身を理解することが一番大事だと思う。でも、これは一番難しいことでもある。日本では生活に追われたり、子育てで、自分の時間を取れない親がたくさんいると思う。もう一方では、あえて自分の時間を取ることを拒む親もいると思う。自分の人生に関して考えたくない、自分を顧みるのが怖い、だからいつも忙しくしているのかもしれない。このような考え方を持っている親もいると思う。
それでも、子供のために自分を理解すべきではないのだろうか。皆さんは自分を理解するためには何が必要だと思う?
それでも、子供のために自分を理解すべきではないのだろうか。皆さんは自分を理解するためには何が必要だと思う?
2010年8月9日
誰からの理解 Part 2
子供は親からの理解を一番求めていると思う。このような考えに至ったのには3つの理由がある。その1つ、「自分の夢や期待を子供に押し付ける親」、についてはPart 1で説明した。ここでは残る2つの理由を説明したいと思う。
2.子供が望んでいる物がわからない親。
子供は言葉を話す前から、自分が欲しいものを周りの人に伝えようとする。それでも、子供自身は欲しがる理由を理解してないかもしれない。親は子供の伝えていることを理解できても、言葉より深い、本能的な理由を理解していないかもしれない。
未知の世界に生まれて来る子供達は、自分が安心できる環境を求める。そして、幼い頃から子供は親がその安心感を与えてくれるとわかる。自分が愛されていることや必要とされていることや自分の存在に意味があることの確認を親に求める。これは当たり前なことだと思わない?それでも、親の考えや行動と子供が求めていることが異なることをたくさん見てきた。
2.子供が望んでいる物がわからない親。
子供は言葉を話す前から、自分が欲しいものを周りの人に伝えようとする。それでも、子供自身は欲しがる理由を理解してないかもしれない。親は子供の伝えていることを理解できても、言葉より深い、本能的な理由を理解していないかもしれない。
未知の世界に生まれて来る子供達は、自分が安心できる環境を求める。そして、幼い頃から子供は親がその安心感を与えてくれるとわかる。自分が愛されていることや必要とされていることや自分の存在に意味があることの確認を親に求める。これは当たり前なことだと思わない?それでも、親の考えや行動と子供が求めていることが異なることをたくさん見てきた。
2010年8月2日
誰からの理解?
他者に責任を求める前に相手に置かれた状況や相手がどういう人物であるかという点を理解することが必要である。では、子供に関しては誰からの理解が一番必要なのだろうか? 社会や学校の先生たち、友達や親戚、それとも家族や親の理解だろうか?皆さんは子供の頃、だれから一番理解されたいと感じていただろうか?
ほとんどの子供は親からの理解を一番欲しがっていると思う。自分を生んでくれて、育ててくれる人が一番大切だから、その人たちに理解されたいのではないのだろうか。そして親は自分の子を一番良く理解できる立場に立っていると思う。でも実際に、大半の親は本当には自分の子供を理解していないと思う。
僕がこのように考えに至ったのには3つの理由がある。そしてそれらは、アメリカと日本、どちらの国でも観察されたことだ。
ほとんどの子供は親からの理解を一番欲しがっていると思う。自分を生んでくれて、育ててくれる人が一番大切だから、その人たちに理解されたいのではないのだろうか。そして親は自分の子を一番良く理解できる立場に立っていると思う。でも実際に、大半の親は本当には自分の子供を理解していないと思う。
僕がこのように考えに至ったのには3つの理由がある。そしてそれらは、アメリカと日本、どちらの国でも観察されたことだ。
2010年7月30日
責任より理解
何か起こると責任人を探す。でも、それで次の事件が起こるのを防げるのだろうか?僕は防げないと思う。それでは、何かが起こるのを防ぐには何をすれば良いのだろうか。
例えば、学生の暴力事件を防ぐには、生徒に暴力はいけないと説教すればいいのだろうか?それは違うと思う。皆さんは骨折したら、それを無視して、痛み止めを飲む?熱がでたら、熱を下げる薬だけを飲む?悪い症状が出たら、症状だけを治療するのではなく、原因を見つけけて治療する。子供が喧嘩したら、そこで「辞めなさい」と怒鳴るだけで喧嘩を終わらせるのではなく、どうして喧嘩が始まったかを話し合う。
でも、暴力事件に対しては普通そのように原因をするのだろうか。それとも、犯人に責任を取らせて、それで終わらせるのだろうか。
僕は暴力は悪いことだと思うけど、それは病気でいうところの症状にすぎないと思う。重要なのは「誰のせい」ではなく、「どうして起こった」だと思う。皆さんはこの2つの質問は同じだと思う?それは何を求めるかという目的によって違うと思う。責任を求めていたら、全く同じ質問になるけれども、理由を理解しようとしていたら、全く違う質問になる。
例えば、学生の暴力事件を防ぐには、生徒に暴力はいけないと説教すればいいのだろうか?それは違うと思う。皆さんは骨折したら、それを無視して、痛み止めを飲む?熱がでたら、熱を下げる薬だけを飲む?悪い症状が出たら、症状だけを治療するのではなく、原因を見つけけて治療する。子供が喧嘩したら、そこで「辞めなさい」と怒鳴るだけで喧嘩を終わらせるのではなく、どうして喧嘩が始まったかを話し合う。
でも、暴力事件に対しては普通そのように原因をするのだろうか。それとも、犯人に責任を取らせて、それで終わらせるのだろうか。
僕は暴力は悪いことだと思うけど、それは病気でいうところの症状にすぎないと思う。重要なのは「誰のせい」ではなく、「どうして起こった」だと思う。皆さんはこの2つの質問は同じだと思う?それは何を求めるかという目的によって違うと思う。責任を求めていたら、全く同じ質問になるけれども、理由を理解しようとしていたら、全く違う質問になる。
2010年7月26日
誰のせい?
日本で学生が起こす暴力事件は毎年増える一方である。もし、皆さんの近くの学校で暴力事件が起きたら、最初のに何と思うだろうか?「犯人の子の親は何やっている」か「学校は何やっている」というように思うのではないだろうか。 誰のせい、誰が責任を取る、こんな考えが普通だと思う。
では、皆さんはこの暴力事件の傾向は誰のせいだと思う?多分、親のせいだと思う人は多いだろう。僕は次のようなことを良く聞きます。近頃の親は子供を甘やかし過ぎて、しつけをちゃんとしていないからこうなる。親は子供を育てる責任がある。子供はまだ未熟だから、大きい過ちは親の責任。
でも、こう考えていいのだろうか?
では、皆さんはこの暴力事件の傾向は誰のせいだと思う?多分、親のせいだと思う人は多いだろう。僕は次のようなことを良く聞きます。近頃の親は子供を甘やかし過ぎて、しつけをちゃんとしていないからこうなる。親は子供を育てる責任がある。子供はまだ未熟だから、大きい過ちは親の責任。
でも、こう考えていいのだろうか?
2010年7月22日
学校は安全?

逆に皆さんは日本の学校の安全性に対してどんなイメージをもっている? 僕は日本の治安はいいし、日本では銃もないから、学校もそうじゃないのかと思っていた。でも、来日してからニュースで聞いた事件や学校で経験から、実際はどうだろうと思い始めた。
この疑問を解決するためにアメリカと日本の学校で起こる暴力事件に関して調べてみた。その結果を皆さんに伝えたいと思う。
2010年7月17日
悲しい逆説に対する考え
Part 1: 悲しい逆説的状況
Part 2: 悲しい逆説の根源?
追い込まれた状況から逃げられないと、人は誰かに助けを求めようとする。しかし、日本ではこれがとても難しいというのは当たり前だと思う。日本では、人は自分のことで精一杯で、他人の問題を押し付けられるのは嫌だし、誰かが助けれくれるだろうから、自分はしなくても良いと思うのではないのだろうか。助けを求めようとする人たちは冷たい目で見られて、苦しんでいるのに迷惑扱いされ、もっと傷つけられ、追い込まれる。周りの人が自分の苦しみに対してどう反応をするのか知っている人は誰にも助けを求めるず、自分の苦しみに溺れ死ぬ。
でも、皆がこうではないと僕は信じている。少ないかもしれないが、人の助けになりたいと思う人が絶対いる。自分が同じような苦しみに追い込まれた経験したから、他人の気持ちを理解できて、何かしてあげたい。ただ、どうすれば良いか分からない。
では、どうすれば良いのか?
Part 2: 悲しい逆説の根源?
追い込まれた状況から逃げられないと、人は誰かに助けを求めようとする。しかし、日本ではこれがとても難しいというのは当たり前だと思う。日本では、人は自分のことで精一杯で、他人の問題を押し付けられるのは嫌だし、誰かが助けれくれるだろうから、自分はしなくても良いと思うのではないのだろうか。助けを求めようとする人たちは冷たい目で見られて、苦しんでいるのに迷惑扱いされ、もっと傷つけられ、追い込まれる。周りの人が自分の苦しみに対してどう反応をするのか知っている人は誰にも助けを求めるず、自分の苦しみに溺れ死ぬ。
でも、皆がこうではないと僕は信じている。少ないかもしれないが、人の助けになりたいと思う人が絶対いる。自分が同じような苦しみに追い込まれた経験したから、他人の気持ちを理解できて、何かしてあげたい。ただ、どうすれば良いか分からない。
では、どうすれば良いのか?
2010年7月13日
悲しい逆説の根源?
バブル経済の崩壊の影響で日本の自殺率の急増は社会にとって重大な問題となっている。この問題を解決するには原因を明らかしないといけないが、自殺者が意志を残さない限り、理解するのは難しい。だから、具体的な原因を見るより、その奥深くに潜んでいる状況を探ってみたいと思う。でも、これは単に僕の意見であり、これを読んでいる皆さんとの会話の始まりだと思っている。
日本の歴史には「切腹」という風習があった。この概念、特に、「死で家族の名誉を取り戻す」や「自分の命で詫びる」などはまだ日本で生きているではないだろうか。でも、日本の自殺率への影響は小さいと思う。この考えを除くと、自殺問題は日本やアメリカ、そしてその他の諸国、と同じ状況で自殺問題が起きていると思わざるを得ない。
日本の歴史には「切腹」という風習があった。この概念、特に、「死で家族の名誉を取り戻す」や「自分の命で詫びる」などはまだ日本で生きているではないだろうか。でも、日本の自殺率への影響は小さいと思う。この考えを除くと、自殺問題は日本やアメリカ、そしてその他の諸国、と同じ状況で自殺問題が起きていると思わざるを得ない。
2010年7月9日
悲しい逆説的現状
恵まれた国の中でアメリカが一番恵まれていると言う人は多いと思う。力や名誉や富で豊かな国で、個人主義のおかげで人は自由。人は自分の為に生きて、自分の幸せを掴むのが最優先。世界から見ればはアメリカでの生活は何にも抑えられず、自分が独りで生きていけるイメージがあるのだろうか?
一方、日本は平和な国で人々が自己を押さえ、集団や社会の為に生きているイメージが強いだろう。人々がお互いを助けあうからこそ平和な日々に恵まれている。
これを考えるとアメリカの方が自殺問題が大きいことが当然のように思える。でも、現実を見るとそうではないと気付く。それだけではない、日本の自殺率はアメリカの2倍。そして世界の国の中で4位、G8の中で1位だと分かる。
一方、日本は平和な国で人々が自己を押さえ、集団や社会の為に生きているイメージが強いだろう。人々がお互いを助けあうからこそ平和な日々に恵まれている。
これを考えるとアメリカの方が自殺問題が大きいことが当然のように思える。でも、現実を見るとそうではないと気付く。それだけではない、日本の自殺率はアメリカの2倍。そして世界の国の中で4位、G8の中で1位だと分かる。
2010年7月3日
僕の世界を変えたボランティア経験 Last Part
Part 3 (http://tcknomekara.blogspot.com/2010/07/part-3.html) の続き
3: 本当に生きることは、どういうことか
グアテマラでの経験の中で一番印象に残ったのは人々の生き方だった。それまでの僕の生き方と比べると、この 人たちの生活は不安定で貧しい。ゴミ捨て場の生活や内乱後の混乱は平和に囲まれたアメリカや日本の生活とは比べ物にならない。それでも、僕は日本やアメリカ にないものを見つけた。それは本当に生きている人たち。
グアテマラの人たちの生活に衣食住の安定はがなかった。皆は必死に毎日を生きようと していた。この人たちと暮らした僕は最初は皆の生活に不満を感じた。「こんな生き方で良いのか」とか「この人たちは何もない」とか思った。アメリカでの恵まれ た暮らしが恋しくなった。でも、それもすぐに変わった。だって、この人たちは不満ではなかった、逆に本当に喜んで毎日生きていた。僕は日本でもアメリカでも感じたことがなかった幸せを肌で感じた。「そして考えた、「どうして何もないグアテマラでこんなに生き生きしている人がいるのに、恵まれた国にはこうやって生きる人はいないの?」
この人たちは衣食住を手に入れるので精一杯。恵まれて平和な生活を送る僕たちはこれが当たり前にあるように生きている。そして社会はそれだけでは幸せになれないと言う。最新技術がないと幸せになれない、体がこんな形だと幸せになれない、こうやって生きていか ないと幸せになれない。僕たちは社会の嘘のせいで満足できなくなった。まるで子供のように必要な物より欲するものに目を向けて生きている。
3: 本当に生きることは、どういうことか
グアテマラでの経験の中で一番印象に残ったのは人々の生き方だった。それまでの僕の生き方と比べると、この 人たちの生活は不安定で貧しい。ゴミ捨て場の生活や内乱後の混乱は平和に囲まれたアメリカや日本の生活とは比べ物にならない。それでも、僕は日本やアメリカ にないものを見つけた。それは本当に生きている人たち。
グアテマラの人たちの生活に衣食住の安定はがなかった。皆は必死に毎日を生きようと していた。この人たちと暮らした僕は最初は皆の生活に不満を感じた。「こんな生き方で良いのか」とか「この人たちは何もない」とか思った。アメリカでの恵まれ た暮らしが恋しくなった。でも、それもすぐに変わった。だって、この人たちは不満ではなかった、逆に本当に喜んで毎日生きていた。僕は日本でもアメリカでも感じたことがなかった幸せを肌で感じた。「そして考えた、「どうして何もないグアテマラでこんなに生き生きしている人がいるのに、恵まれた国にはこうやって生きる人はいないの?」
この人たちは衣食住を手に入れるので精一杯。恵まれて平和な生活を送る僕たちはこれが当たり前にあるように生きている。そして社会はそれだけでは幸せになれないと言う。最新技術がないと幸せになれない、体がこんな形だと幸せになれない、こうやって生きていか ないと幸せになれない。僕たちは社会の嘘のせいで満足できなくなった。まるで子供のように必要な物より欲するものに目を向けて生きている。
2010年7月1日
僕の世界を変えたボランティア経験 Part 3
Part 2(http://tcknomekara.blogspot.com/2010/06/part-2_28.html)の続き
2:どんな障害があっても人は分かり合えると分かった。
2週間半の間、僕たちはグアテマラの人々と共に暮らし、一緒に汗をかきながら働いた。そして、3日間、一人でグアテマラの家庭ホームステイをした。どこでも、グアテマラの人たちは言葉が通じない僕を受け入れてくれた。この最初の 一歩で分かち合える道が造られた。それを感じた僕は、どんな手段を使っても踏み出そうとした。時間がかかったけど、伝わった。そして僕は気付いた。
人と分かり合えるために一番大事なのは人をありのままに受け入れることだ。これは当たり前だと思うけど、人を無条件 で受け入れるのはとても難しいことだ。グアテマラのの人々は外国人の僕たちを無条件で受け入れてくれた。家を他人に開けて、ともに生活するのを許してくれ た。
2:どんな障害があっても人は分かり合えると分かった。
2週間半の間、僕たちはグアテマラの人々と共に暮らし、一緒に汗をかきながら働いた。そして、3日間、一人でグアテマラの家庭ホームステイをした。どこでも、グアテマラの人たちは言葉が通じない僕を受け入れてくれた。この最初の 一歩で分かち合える道が造られた。それを感じた僕は、どんな手段を使っても踏み出そうとした。時間がかかったけど、伝わった。そして僕は気付いた。
人と分かり合えるために一番大事なのは人をありのままに受け入れることだ。これは当たり前だと思うけど、人を無条件 で受け入れるのはとても難しいことだ。グアテマラのの人々は外国人の僕たちを無条件で受け入れてくれた。家を他人に開けて、ともに生活するのを許してくれ た。
2010年6月28日
僕の世界を変えたボランティア経験 Part 2
ゴミ捨て場で刺激を受けた初日から2週間半僕たちはグアテマラで暮らし、いろいろな人に出会って、様々なことを経験して、汗と涙のボランティア活動を した。この経験は僕たちが持っていた小さい世界観を崩した。3年前(1996)にやっと終わった14年間の内乱を生き延びた国民たちが一生懸命生きて いる姿と、どんな不利な状況を乗り越える志を持った人々の印象は目と心に刻まれた。僕の世界観は変わった。
どのように変わったというと:
1:Part 1に書いたように、どんなに時間がかかっても、どんなに損することがあっても、他人、特に子供と関わり、良い影響を与えようとする覚悟と志を得た。でも、覚悟と言って も、恵まれた環境で育った人間が持つような生易しい覚悟ではない。もちろん恵まれた環境で生きてても皆苦労するし、悪いこともある。それを軽く見ない。でも、平和な日 々を過ごしている僕たちの欲望の達成邪魔するものと、世界の大半の人の生活を脅かすものとでは、格が違う。
世界では、今週はいつ食べられるのかと悩む人たち、今 日買い物に行くとテロの爆弾で死ぬかもと恐れるイラク人。今日の一日が最後かもしれない状況で必死に生きようとする人たち。この人たちは死ぬ覚悟で一生 懸命生き延びようと戦っている。
グアテマラの人たちもこの覚悟で生きていた。それに比べると僕の覚悟は弱いなと思った。そして、自分の弱 い覚悟をグアテマラで捨てて、恵まれた、平和な生活に戻っても、グアテマラの人たちの覚悟を心に刻み、一生懸命その覚悟に応じるように生きるようと 決心した。それからの11年間は成功したときより失敗したときの方が多いかもしれないけど、僕は諦めず毎日一生懸命戦っている。
続きは後 ほど
どのように変わったというと:
1:Part 1に書いたように、どんなに時間がかかっても、どんなに損することがあっても、他人、特に子供と関わり、良い影響を与えようとする覚悟と志を得た。でも、覚悟と言って も、恵まれた環境で育った人間が持つような生易しい覚悟ではない。もちろん恵まれた環境で生きてても皆苦労するし、悪いこともある。それを軽く見ない。でも、平和な日 々を過ごしている僕たちの欲望の達成邪魔するものと、世界の大半の人の生活を脅かすものとでは、格が違う。
世界では、今週はいつ食べられるのかと悩む人たち、今 日買い物に行くとテロの爆弾で死ぬかもと恐れるイラク人。今日の一日が最後かもしれない状況で必死に生きようとする人たち。この人たちは死ぬ覚悟で一生 懸命生き延びようと戦っている。
グアテマラの人たちもこの覚悟で生きていた。それに比べると僕の覚悟は弱いなと思った。そして、自分の弱 い覚悟をグアテマラで捨てて、恵まれた、平和な生活に戻っても、グアテマラの人たちの覚悟を心に刻み、一生懸命その覚悟に応じるように生きるようと 決心した。それからの11年間は成功したときより失敗したときの方が多いかもしれないけど、僕は諦めず毎日一生懸命戦っている。
続きは後 ほど
2010年6月26日
僕の世界を変えたボランティア経験 Part 1
僕は中学の頃から色々なボランティア活動をやって来ました。この様々な経験で僕は色々な人と出会い、関わり、この人たちの話を聞きました。この様々な出会いと経験に影響され、僕の人生は少しずつ変わりました。僕のボランティア経験の中で、人生に一番大きく影響したのは高校3年の夏に起きたことでした。その夏、僕は2週間半グアテマラでボランティア活動をしました。そこで僕の目と心に刻まれたことを皆さんに伝えたいと思います。
活動初日、グアテマラの首都、グアテマラシティー内を車でツアーをしました。途中で高い壁に囲まれたお金持ちや政治家や外交官が住んでいるゲートを付いたコミュニティーを見ました。それから、車で10分も経たない内にグアテマラシティーのゴミ捨て場に行きました。ゴミの山の中に人や段ボールとかで作らて家を見ました。ガイドさんの話によると市民の大勢(何パーセントかは覚えてないけど、50%は超えてた気がする)がこのゴミ捨て場に住んでいたそうです。目の前にゴミの中から売れる物を探している大勢の人々のイメージか心が痛みました。
活動初日、グアテマラの首都、グアテマラシティー内を車でツアーをしました。途中で高い壁に囲まれたお金持ちや政治家や外交官が住んでいるゲートを付いたコミュニティーを見ました。それから、車で10分も経たない内にグアテマラシティーのゴミ捨て場に行きました。ゴミの山の中に人や段ボールとかで作らて家を見ました。ガイドさんの話によると市民の大勢(何パーセントかは覚えてないけど、50%は超えてた気がする)がこのゴミ捨て場に住んでいたそうです。目の前にゴミの中から売れる物を探している大勢の人々のイメージか心が痛みました。
2010年6月24日
ボランティアの大切さ
ボランティア活動とは基本的に人の生活を無償で手伝うことです。これは様々な形で行うことになりますすが、すべて、対象とする人たちを手伝ったり助けたりするのです。アメリカではホームレスのシェルターに行って食べ物を作って配ることができる。寄付された食べ物の倉庫に行って整理する。子供のスポーツを手伝う。もっと大きく考えると他の国に行って家を建たり、何かの援助活動をする。ボランティア活動を経験した人に聞くと、自分が手伝えたことより得たことが多かったと言うでしょう。
では、人間、特に子供にはどうしてボランティア活動が必要だと思いますか。 子供は大人ではないからできることが少ないと思いますか。僕は、それは関係ないと思います。子供はどんなに小さくても誰かを手伝えるし、助けられると思います。子供はこの経験で得られることが子供の人生に大きく影響すると思います。子供が得られることは、次も3つに大別できると思います。
では、人間、特に子供にはどうしてボランティア活動が必要だと思いますか。 子供は大人ではないからできることが少ないと思いますか。僕は、それは関係ないと思います。子供はどんなに小さくても誰かを手伝えるし、助けられると思います。子供はこの経験で得られることが子供の人生に大きく影響すると思います。子供が得られることは、次も3つに大別できると思います。
2010年6月22日
我慢&Empathy
人間は生まれたときから自己中心的です。赤ちゃんや子供を見るとそれが良く分かります。自分が世界の中心で、全てが自分の為にあると思って行動しています。これは子供には当たり前な事ですが大人には良くない性質だと思われています。
では、どうやって子供達は大人になるまでに変わるのでしょうか?このことについては、日本とアメリカの考えはある程度、似ていると思います。その考えは「我慢」と「Empathy」の2語で要約できると思います。
我慢と言っても、我慢は日本とアメリカではちょっと違う意味を持ちます。その違いを簡単に言うと「何の目的で我慢しているか」です。日本では我慢は家族や会社や団体の為に自分の自己中心な欲望を抑えることだと思います。自分を抑えて団体の平和を乱さない。これが立て前の役目ではないのでしょうか? アメリカではこれはちょっと違うと思います。アメリカでは団体責任とかの考えもありますが、個人主義がもっと強調されているので、我慢は「自分の欲望を満たすのを先送りする」意味を持っていると思います。今自分の欲望を抑えたら後でもっと良いことが起こるよ。後で欲望がかなうと待った分満足するよ。この考えは日本にもあると思いますが日本では団体責任が個人より強調されます。
では、どうやって子供達は大人になるまでに変わるのでしょうか?このことについては、日本とアメリカの考えはある程度、似ていると思います。その考えは「我慢」と「Empathy」の2語で要約できると思います。
我慢と言っても、我慢は日本とアメリカではちょっと違う意味を持ちます。その違いを簡単に言うと「何の目的で我慢しているか」です。日本では我慢は家族や会社や団体の為に自分の自己中心な欲望を抑えることだと思います。自分を抑えて団体の平和を乱さない。これが立て前の役目ではないのでしょうか? アメリカではこれはちょっと違うと思います。アメリカでは団体責任とかの考えもありますが、個人主義がもっと強調されているので、我慢は「自分の欲望を満たすのを先送りする」意味を持っていると思います。今自分の欲望を抑えたら後でもっと良いことが起こるよ。後で欲望がかなうと待った分満足するよ。この考えは日本にもあると思いますが日本では団体責任が個人より強調されます。
2010年6月20日
僕のホームレスの経験
僕はシアトルの小さい私立大学に行きました。この大学の1つの目標は社会正義に関する教育でした。その為に色々なボランティア体験を生徒に与えようとしてました。その1つの体験はホームレス体験でした。シアトルに行ったことある人はご存知だと思いますが、ホームレスが結構大きな社会問題になってます。シアトルの中心部で買い物していると絶対物ごいをしているホームレスの人を見かけます。僕はこの人たちを無視して通り過ぎたこともあるし、お金をあげたこともある、でもこの人たちの状況を知ろうとしなかった。そこで、大学3年の冬に、この体験があると聞いてすぐ申し込みをしました。そして、冬休みの3日間、家に帰らずホームレスになりました。
この経験に参加する大学生は3人チームに分かれられました。服は始まる時に着れるだけのふくとリュックサック1つでした。2泊3日の間、1人1人は$2(約200円)だけ持って行けました。ホームレスと言っても、安全の為、そして本当のホームレスの人たちからシェルターのベッドを取らないように、寝る場所は確保されてました。でも夜10時までそこには行けず、朝5時ぐらいには出なくてはいけなかった。男子は1ヶ月前からひげを剃らないようと指示されていました。食べ物はホームレスみたいに自分たちで確保しなくてはいけませんでした。皆合流する時は1日1回ぐらいでホームレスの為の施設に集まり、そこがホームレスのために何しているかを学びました。他の時間はホームレスと話し合ったり、歩き回ったりしてました。僕のグループはしなかったけど、物ごいをグループもいました。
この経験に参加する大学生は3人チームに分かれられました。服は始まる時に着れるだけのふくとリュックサック1つでした。2泊3日の間、1人1人は$2(約200円)だけ持って行けました。ホームレスと言っても、安全の為、そして本当のホームレスの人たちからシェルターのベッドを取らないように、寝る場所は確保されてました。でも夜10時までそこには行けず、朝5時ぐらいには出なくてはいけなかった。男子は1ヶ月前からひげを剃らないようと指示されていました。食べ物はホームレスみたいに自分たちで確保しなくてはいけませんでした。皆合流する時は1日1回ぐらいでホームレスの為の施設に集まり、そこがホームレスのために何しているかを学びました。他の時間はホームレスと話し合ったり、歩き回ったりしてました。僕のグループはしなかったけど、物ごいをグループもいました。
2010年6月19日
ホームレスの現状
日本ではどの大都市に行っても見つかります。よく見ると線路の下や公園にある段ボールの家や外見で分かるホームレスの人たち。皆さんが最初にホームレスの人を見た時を思い出してください。皆さんはどんな反応をしましたか?日本では知りませんがアメリカでホームレスを見る時はこういう反応が普通だと思います。
「なまけもの、早く仕事しろ」
「中毒者なんて手伝うもんか」
でも、一番ひどい反応はその人たちの存在を認めず歩いて行く人たち。ホームレスの人たちが助けを求めているのに自分の生活に関係ないから無視する。日本人の反応はこれと同じなのでしょうか?
アメリカでは、ホームレスに対してこのような反応が示される原因は教育です。アメリカ一般人はホームレスに関して何も知らないからその人たちを人間以下だと考える。特に日本で、政府が国民や世界からホームレスの問題を隠そうとする。日本ではホームレスに対する教育は全くありません。ホームレスは世界的な問題であり、解決するにはまずそれが社会全体の問題であると認めなくてはならない。アメリカの政府や一部の人たちはこれを認め始めました。日本もそうなるのでしょうか?でも、その前にホームレスの現状を知らないといけない。
「なまけもの、早く仕事しろ」
「中毒者なんて手伝うもんか」
でも、一番ひどい反応はその人たちの存在を認めず歩いて行く人たち。ホームレスの人たちが助けを求めているのに自分の生活に関係ないから無視する。日本人の反応はこれと同じなのでしょうか?
アメリカでは、ホームレスに対してこのような反応が示される原因は教育です。アメリカ一般人はホームレスに関して何も知らないからその人たちを人間以下だと考える。特に日本で、政府が国民や世界からホームレスの問題を隠そうとする。日本ではホームレスに対する教育は全くありません。ホームレスは世界的な問題であり、解決するにはまずそれが社会全体の問題であると認めなくてはならない。アメリカの政府や一部の人たちはこれを認め始めました。日本もそうなるのでしょうか?でも、その前にホームレスの現状を知らないといけない。
2010年6月15日
日本の里親制度
日本の児童福祉制度の中の社会的養護体系は2つに分かれています。1つ目はこの前書いた施設養護です。もう1つは家庭的養護でそれは主に2つ、養子縁組と里親、に分かれています。養子縁組はまた後ほどの話題として、今日は里親制度に関して書きたいと思います。
最初に「里親」とは何でしょうか?
里親制度によると里親は「保護者のない児童、又は保護者に監護されることが不適当であると認められる児童を養育する里親として認定を受けたもの。」すなわち、里親は他人の子供を自分の家で預かって育てることです。里親は預かった子供は実の子供でなくてもりっぱに育てようとする立派な人たちです。子供が心にどんな傷があっても、それを受け入れ、できるだけ普通な生活を与え、その傷をいやす立場に立つのです。
里親の役割
里親制度によると、役割は3つあります。
(1)「子供との間に基本的信頼関係を形成する」
(2)「親や家族のモデルを学ぶこと」
(3)「生活の質の深さを与える」
上記で里親に預けられる子達はこの経験できないからではないでしょうか?施設でもこの役割をある程度はたせると思いますが、子供が必要な程度までは与えられません。だから里親は社会が与えられない経験を子供達に与える。3つとも大切だと思いますが、特に2番は施設では学べないと思います。子供は親と家族との生活で自分が親になった時のモデルを学びます。親は子供自身の将来の姿に大きい影響を与えます。しかし親となる為のモデルがなかったり、大人との信頼を育てる機会がない子達は社会や他人と信頼関係持つことができるのでしょうか?
最初に「里親」とは何でしょうか?
里親制度によると里親は「保護者のない児童、又は保護者に監護されることが不適当であると認められる児童を養育する里親として認定を受けたもの。」すなわち、里親は他人の子供を自分の家で預かって育てることです。里親は預かった子供は実の子供でなくてもりっぱに育てようとする立派な人たちです。子供が心にどんな傷があっても、それを受け入れ、できるだけ普通な生活を与え、その傷をいやす立場に立つのです。
里親の役割
里親制度によると、役割は3つあります。
(1)「子供との間に基本的信頼関係を形成する」
(2)「親や家族のモデルを学ぶこと」
(3)「生活の質の深さを与える」
上記で里親に預けられる子達はこの経験できないからではないでしょうか?施設でもこの役割をある程度はたせると思いますが、子供が必要な程度までは与えられません。だから里親は社会が与えられない経験を子供達に与える。3つとも大切だと思いますが、特に2番は施設では学べないと思います。子供は親と家族との生活で自分が親になった時のモデルを学びます。親は子供自身の将来の姿に大きい影響を与えます。しかし親となる為のモデルがなかったり、大人との信頼を育てる機会がない子達は社会や他人と信頼関係持つことができるのでしょうか?
2010年6月14日
僕がどうやって日本語を勉強した Part 2
3年前, 日本に来てからあるあるごとがきっかけで本格的に漢字の勉強を始めました。その年の秋に学校で漢字検定を受けました。僕は自信を持ってたので8級ぐらい合格できろと思いました。でも、20点も取れなくて悔しかったです。僕は日本語能力試験の1級に合格するのが目標だったので、本当に勉強しないといけないなと思いました。春に5級に挑戦して合格しました。そして冬に日本語能力試験の2級に合格しました。
その一年間でどうやって勉強したか気になりますか?
僕は勉強方法を3つに分けて、それらを同時にやってました。
(1)読書:僕の大学時代に日本に来いてた頃、僕は日本の小1から中3までの国語の教科書を買いました。日本に来るまでただ本棚でほこりをかぶっていてましたがやっとその時、読み始めました。教科書を読みながら知らない漢字や単語を辞書で調べました。小6の教科書を終えてから小学レベルより上の本を買って読みました。今は東野圭吾の小説を読んでいます。
(2)漢字:僕は日本語能力試験の漢字のフラシュカードを買いました。そして国語の教科書で新しい漢字が出てくるとEXCELに入れ、訓と音読みと英語の意味を入力し、自分のための漢字データベースを作って、毎日漢字を書く練習をしました。
(3)日本語のクラス:住んでいた町の近くに交際交流会があって、外国人のための日本語の授業を行っていました。僕は1月にそれを始めました。日本語能力試験の1級を目指してたので、授業ではそのための読解や文法を学びました。週1回でしたが宿題とかもあったのでまじめにやってました。
これが僕の勉強方法でした。去年は JETプログラムの日本語講座の翻訳通訳コースを受講しました。今、僕は、Lang-8.comとツイッターとブログで日本語の書き読みの練習と、漫画やアニメで勉強しています。TEFLの通信授業を受けているのであまり漢字を勉強する余裕がないんです。でもTEFLが終わったらまた漢字の勉強を初めて日本語能力試験の1級に合格するつもりです。
皆さんも何かの目標に向って頑張ってください!!
その一年間でどうやって勉強したか気になりますか?
僕は勉強方法を3つに分けて、それらを同時にやってました。
(1)読書:僕の大学時代に日本に来いてた頃、僕は日本の小1から中3までの国語の教科書を買いました。日本に来るまでただ本棚でほこりをかぶっていてましたがやっとその時、読み始めました。教科書を読みながら知らない漢字や単語を辞書で調べました。小6の教科書を終えてから小学レベルより上の本を買って読みました。今は東野圭吾の小説を読んでいます。
(2)漢字:僕は日本語能力試験の漢字のフラシュカードを買いました。そして国語の教科書で新しい漢字が出てくるとEXCELに入れ、訓と音読みと英語の意味を入力し、自分のための漢字データベースを作って、毎日漢字を書く練習をしました。
(3)日本語のクラス:住んでいた町の近くに交際交流会があって、外国人のための日本語の授業を行っていました。僕は1月にそれを始めました。日本語能力試験の1級を目指してたので、授業ではそのための読解や文法を学びました。週1回でしたが宿題とかもあったのでまじめにやってました。
これが僕の勉強方法でした。去年は JETプログラムの日本語講座の翻訳通訳コースを受講しました。今、僕は、Lang-8.comとツイッターとブログで日本語の書き読みの練習と、漫画やアニメで勉強しています。TEFLの通信授業を受けているのであまり漢字を勉強する余裕がないんです。でもTEFLが終わったらまた漢字の勉強を初めて日本語能力試験の1級に合格するつもりです。
皆さんも何かの目標に向って頑張ってください!!
登録:
投稿 (Atom)